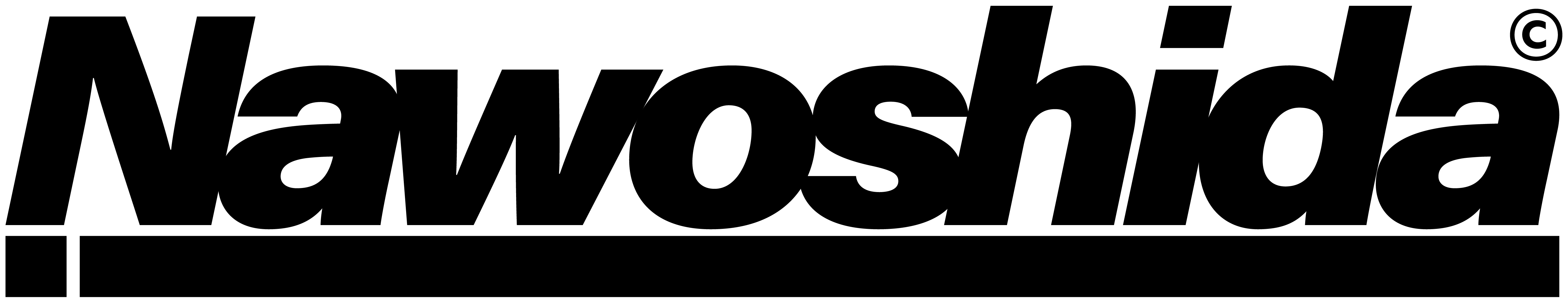僕は、改めて姿見の前に立っていた。衣類など一切身につけないままに、自分の柔らかな毛並を鏡越しに凝視する。中性的な顔立ちの僕が、僕のことを見つめ返して来ているのが、どこか小っ恥ずかしさを感じさせてくる。
視線をさらに下へ下へと押し下げていくと、華奢な鎖骨のラインから、桃色の控えめに主張する乳首、白く短い毛が生えそろうへそ回りへと続いていく。僕はその身体を優しく撫で上げると、くすぐったさと心地よさが交い混ぜになった享楽に、意識せずとも口角が上がってしまう。
へその下まで到達した視線は、いよいよ僕自身の中心点へと続いていった。ぷるりぷるりと小刻みに跳ね上がっては、小さな亀頭を包み込む包皮を濡らしている、可愛らしく勃ち上がったおちんちんに、僕はついに釘付けになる。
「……とっても、可愛いな、僕って」
僕の、僕だけの特別なおちんちん。三毛猫種のネコ獣人である僕には、それを持つこと自体がただただ特別だった。
ネコ獣人の中でも、三毛猫種は遺伝的に、オスの個体は誕生するはずのないものとして扱われている。過去にもそういった個体の出生例はあるらしいが、皆一様に何かしらの知的・身体的・発達的障害を持っていたり、生殖能力が喪失していたりといった問題を持って生まれてきている事例ばかりだといわれている。
けれど、僕は特別だった。何の障害もなく1█年間生きてこられたし、さらには僕のおちんちんは、他の個体とは違って生殖能力もしっかりと備わっていた。両親が言うには、あまりにも前例のない話だっただけに、しばらくの間世間の目から僕を守るために、僕はメスとして育てられてきた期間があった。両親からすれば、雄の三毛猫種が生まれること自体ショックそのものなんだろう。些か受け入れがたい現実として映っていたのかもしれない。「オスの三毛猫種」というだけで、差別的に扱われることも少ない社会であるがゆえに、そのような行動に至ったんだろうということは、今になればよく理解できる。
けれど、そのような育てられ方は、僕のアイデンティティにとって、とてつもなく大きな影響を及ぼした事は間違いない。
僕は、メスになりたかった。
別に、僕がオスであることが嫌だとは全く思っていない。むしろ、そんな特別な僕が好きといえるまである。僕がオスであることそのものを否定するつもりもないし、このおちんちんが嫌いだとか、そういった感情も持ってはいない。でも、僕はメスネコになりたかったし、今でもなりたいと思っている。この特別なおちんちんをなくせば、僕もメスになれるのかな、と、そんな安直なことを考えることも少なくはない。けれど、このおちんちんは、三毛猫種で唯一無二なおちんちんだから。そんなおちんちんを取ってしまうなんてことは、どこかもったいないような、残念な気持ちになってしまうため、やはり僕は考えたくなかった。
物心がついた頃から両親が買い与えてくれた女児服を着こなすのが、僕はずっと好きだった。両親が服を買わなくなってからも、僕はメス用の服を買い漁るようになった。今僕が全裸になったのも、僕自身の姿をハッキリ見たかったというだけではなく、ちょうど通販サイトで購入した服を試着したかった、というのが本当の理由だった。
「うん、ちゃんとピッタリだ……」
服を箱から取り出して、タグを外し終えると僕はすぐに着こなしてみた。縞模様の柄が入ったブラジャーとショーツを身につけると、それだけで僕はメスになった気がした。小さな乳首が厚手の布に覆われている感覚に、僕はどこか興奮を覚えた。皮被りのおちんちんがショーツの中で窮屈そうに藻掻く度、しびれるような気持ちよさが全身に木霊する。僅かに漏れる嬌声を抑えようと試みながら、箱に残っていた英文の書かれたハートデザインのアウターシャツの裾に腕を通し、濃い青のジーンズ生地で出来たホットパンツに足と尻尾を通した。
「す、すごい……すごく、似合ってる」
もう一度、僕は姿見の前に立ち尽くす。ただ何もせず立っているだけなのに、そこに映る僕の容姿はあざとさといやらしさで溢れていた。肩と臍が露出した上半身と、太ももの際までさらけ出した下半身。あまりにもそれは扇情的としか言えないほどに、淫靡に映った。これが、本当に僕の姿なのか、メスになった僕はこんなにも可愛いのかと思えば思うほど、自分自身に欲情してしまう。狭苦しいホットパンツに押さえつけられたおちんちんはガチガチに勃起して、はやく外に出せとせがんでいる。少し誘惑するようなポージングを決め込めば、僕のおちんちんにクリティカルヒットを飛ばしてしまう。
「んぐぅっ……かわいい、かわいいよ、悠介……っ♡」
僕は僕の名前を呼んでみながら、ホットパンツのジッパーをジジジ、と下ろした。ショーツを少しずらすと、ぴょこん! と元気よく、愛くるしいおちんちんが顔を出す。既に先走りでドロドロに汚れたおちんちんは、皮越しでも空気に触れるだけでピリピリとしびれている。
そっと僕は指でおちんちんをつつくと、甘ったるくも鋭い快感がビリッと伝わる。メスの格好をした自分の股間から、オスの象徴が飛び出しているアンバランスさにギャップを感じて、僕はさらに興奮を高めていった。
ショーツをさらに下ろして、僕はタマタマまでさらけ出してみる。苦しく締め付けるものがなくなった男性器がぷるぷると震えながら自由を満喫している。おちんちんもタマタマも、メスネコが近くにいると思い込んでいるのか、さらにオス臭いフェロモンを振りまきながら必死にセックスアピールに勤しんでいる。
「す、すっごい元気だよ、おちんちん、元気すぎる……っ」
このおちんちんはかれこれ数ヶ月、一度もオスイキさせて貰えなかったおちんちんである。長い間ほぼ一切おちんちんに触るなんてことをしなかったためか、少し指で小突くだけで、もっと刺激が欲しいと言わんばかりに背を伸ばして、新たな刺激を乞うように、包皮から滴る先走りを床へと溢していた。優秀な三毛猫タマタマの方も、中に元気な精子がぎゅうぎゅう詰めになっている気がする。柔らかい白毛袋が張り詰め、もぞもぞと伸び縮みを繰り返す姿から想像するに、その可能性は濃厚だった。
「ふっ……ぐっ、だめ、だめだよ、そんなに暴れても、今日もこっちを使うからね……っ」
けれど、僕はそんな我慢ばかり強いられているおちんちんには一切触れるつもりはなかった。まだまだこの子には我慢して貰わないといけない。だって僕は今はメスだから。メスはおちんちんでイったりするものじゃないから。一生懸命に勃ち上がって、僕自身に媚びるかのように左右へ揺れるおちんちんを無視して、あらかじめ準備していたグッズを手に、僕は鏡の前に腰を下ろした。
ぐちゅぐちゅとした音が、肉球でディルドを撫でる度に部屋に響き渡る。15cmは超えるサイズを誇る黒いシリコン製のディルドは、僕が両親に内緒で購入した一番巨大なものだ。人肌に温めたそれがテラテラと窓から差す夕陽に反射しているのが、いつみても艶めかしくて、僕のえっちな気分をさらに高めさせてくれる。
僕はホットパンツだけを脱ぎ取り(ずらして行為に挑もうとしたが、材質が固く伸縮しないためやむなく脱いだ)、既に先走りでどろついたショーツのお尻の部分だけずらして、ローションを滴らせた指を、後ろの穴に押し込んでいく。腸を傷つけないように鋭かった爪も切ったお陰で、安心してお尻をほぐす事が出来る。
「あっ、うっ……んゃ、ぁ……」
僕が甘ったるい声を溢す度、ぬちゅぬちゅと音を立てて貪欲に指を貪るアナル。既に腸液が溢れてきているのか、ひくひくと括約筋が指を締めてくる。程よい締め付けになったところで、さらに指を追加してじっくりほぐしていく。今日はどうやら僕自身の調子も良い日らしく、ほぐす段階で既にじんと響くような性的快楽が下半身に広がっていく。おちんちんの勃起も未だ収まることなく、後ろから与えられるじんじんと響く性感に酔いしれ、僕と同様に先端からだらりと涎を溢していた。
「も、もう、いいかな……よし」
ある程度すんなりと指を受け入れるようになったところで、僕はいよいよディルドを片手にごろりと寝そべる。クッションを挟んで壁にもたれかかるような体勢で姿見にお尻を開けっぴろげにすると、羞恥で心がいっぱいになる。その精神的な気持ちよさもまた、僕の性感を高める上でのスパイスになっていた。
一匹のメスネコが、恥も見聞もない姿を晒している。それだけで、充分すぎる興奮を呼び覚ましてくるのだ。
ディルドを持つ手が震えながらも、ぱくぱくと次なる刺激を待ち望むかのように開閉する縦に割れたアナルに、その切っ先を向ける。
ずぷぷっ、ずるるっ。
「ふぅっ、んぁっ、ぐぅ────っ!!♡♡♡」
びっくん、びっくん、びっくん!
極太のディルドが、ゆっくりと確実に胎内へと貫いてくる。ゾワッと全身の毛が逆立ち、さっきまで揺れていた尻尾がピンと張ってしまう。そう、この感覚……身体の内側を強引に圧迫されるような感覚が、本当に癖になる。直腸内でぐいぐいとディルドが押される度、一番気持ちの良いところがピンポイントで刺激される。声にならない声が、手で押さえた口から我慢できずに漏れ出し、跳ね上がる腰に合わせて、まともに精液を吐き出させて貰えていないメスおちんちんが右へ左へと駄々をこねている。
全身が”気持ちいい”で溢れている。メスとしての快楽が、僕という個体を徹底的に悦ばせてくれている。前立腺をディルドが小突くたびに、フワフワとした気持ちよさが溢れかえり、目尻に大粒の雫をため込んでしまう。まさに、今この瞬間の僕はメスそのものだ。おちんちんなんかなくたって、僕はメスとして気持ち良くなれるんだ。
なにより、他の三毛猫種のオスが持ちたくても持てなかった「使えるはずのおちんちん」を無駄に持て余して、世界で一本しかない特別なおちんちんを使えない飾りものみたいに蔑ろにしてまで、ただがむしゃらにメスらしさを求め続ける行為に対して、僕は強烈な背徳感を感じて仕方がなかった。
「え、へへへぇ……すっごい、すっごい気持ちいい……やわらかメスネコお尻まんこのほうが、クソザコ三毛猫おちんちんなんかよりずっと気持ちいいよ……っ!♡ せっかく精子を作れるタマタマを貰っておいてっ……もう3ヶ月以上オスイキなんてしてないっ♡♡ だって、だってお尻まんこのほうが、ずっと生殖器として優秀だもんっ♡ おちんちんは性器失格っ♡ こんなの、ただのクソザコおしっこホースでしかないんだよ♡♡ タマタマだって、メスに捧げられないゴミ精子をため込んだゴミ袋でしかないのっ♡♡ だからっ、この子たちはっ♡ 一生触ってなんてあげないっ♡♡ あぅっ、はぁ……っ♡ もっと、そう、もっと突いて、メスイキっ……あっ、あっ……!!♡♡♡」
マゾヒズムたっぷりな罵倒を込めて、鏡の向こうの自分に対して投げかけるように飛び出す淫語の数々。柔毛とフローリングを粘液で濡らし、あられも無い姿でよがり狂う己があまりにもいやらしすぎて、僕はとうとう我慢なんてできなくなっていた。
ぶるんぶるん跳ねるおしっこホースや、ぎゅうっと縮こまったゴミ袋には目もくれず、鏡の僕のディルドを咥え込むアナルばかりに視線がいっていた。美味しそうにシリコン素材を頬張る穴は収縮と緊張を繰り返すペースを徐々に速めていく。もうすぐ、もうすぐあのヤマ場を迎える。浮いた腰が小刻みに震えてしまう。
僕は身体に響く快楽の波に乗りながら、ディルドを床に立ててしゃがみ込み、そのまま一気に奥へと突くように座り込んだ。
「あっ、やっ……♡♡ く、来るっ、来ちゃうっ♡ いっっっっっ♡♡♡♡」
びっくんっ! びくんっ! ぞくぞくぞくぞくっ♡♡♡
ぶるんっ! びんっ! ちょろっ♡ ぶしゅっ♡ じゅぶぶっ♡♡ じょぼじょぼっ♡♡♡
最奥までディルドが押し込まれるのが遅いか早いかのところで、僕はついにメスイキする。熱々の熱がお尻の奥から全身になだれ込むようなオーガズムと同時に、全身が仰け反って言うことを聞かなくなる。ぐちゃぐちゃと淫靡な音を響かせ続けるアナルは大量の腸液が隙間からこぼれ落ち、床に大きな水たまりを生み出している。ここまで徹底的に避けられてばかりの最大限まで勃起した可哀想なおちんちんも、僕と同じように仰け反っては、透明な熱い体液を蛇口を捻った時のように迸らせ、周囲を青臭く染め上げていた。
そう、これは潮だ。僕は潮を吹いたんだ。今までのアナルオナニーでも数回しか経験の無い潮吹きに、それを放り出すほどの熱の籠もった最大級の絶頂に感動すら覚えたまま、僕は白目を剥いたまましばらく動けなかった。
それから数十分ほどが過ぎて、さっきまでの熱もある程度冷めた頃。僕は冷えた体液にまみれたまま目が覚める。毛に染みこんだ体液が乾いて不快感を示しながらも、起き上がって見えた事後の自分を見れば、その不快感さえもすぐに霧散してしまう。
気を失っている間もディルドを咥え込んで離さなかったメスアナル。無理矢理潮吹きさせられて欲求不満なまま勃起し続けていたメスおちんちん。ここまで来てまだ吐き出せない精子を抱え込んで悶えているメスタマタマ。そしてそれを眺めて下卑た笑みを浮かべてしまっている自分の顔。その全てが、僕の性的欲求を再点火させるに足りる要素として働いていた。
「うぅ……また、やりたくなって……♡」
こんな姿を見てしまえば、もう止まらないじゃないか。買ってすぐに汚してしまった服のことなどもはや気にもせず、姿見に映る僕を見続ければ、熱く滾る興奮はさらに昂ぶってしまうのだった。